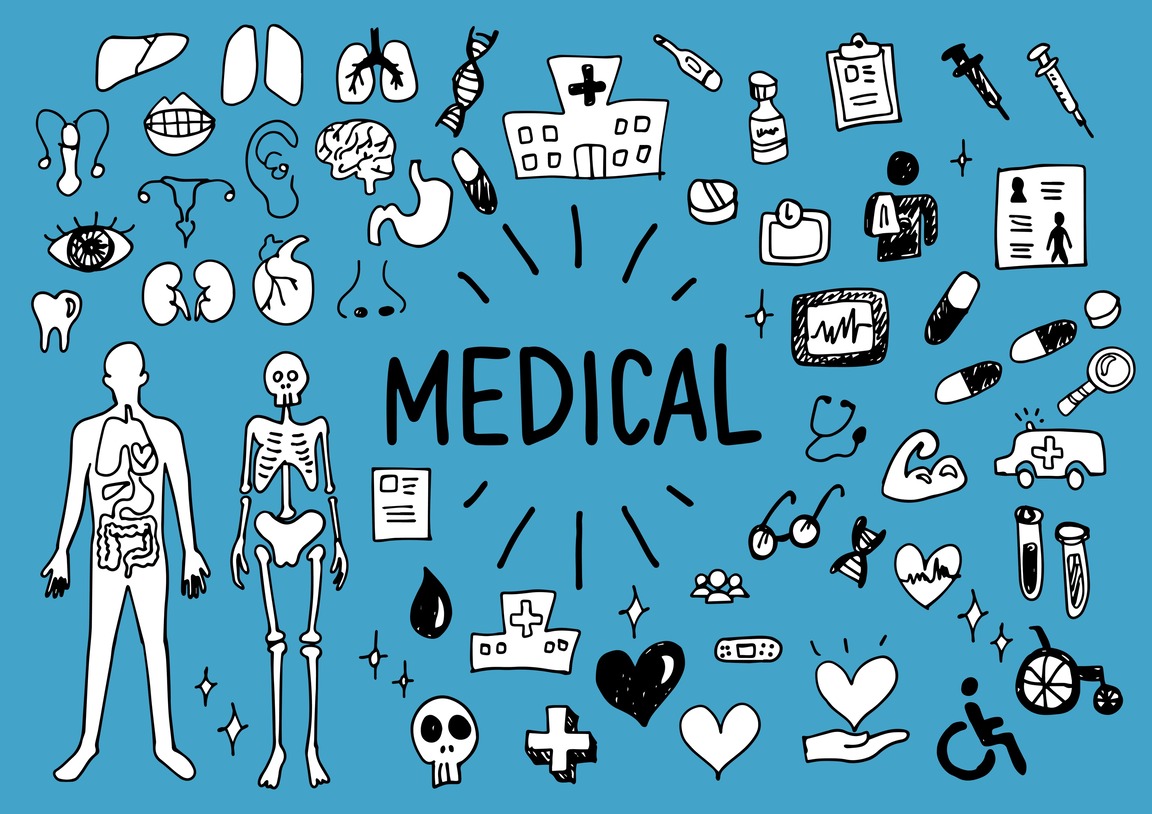
| 項目 | 詳細 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 試験日 | 2025年2月8日(土)、9日(日) | 2日間の実施 |
| 試験地 | 北海道、宮城、東京、新潟、愛知、石川、大阪、広島、香川、福岡、熊本、沖縄 | 当日の移動時間を考慮しておきましょう |
| 願書配布機関 | 2024年10月中旬以降 | 大学や郵送で請求可能。郵送の場合、手元に届くまで約1週間かかるため早めの請求をおすすめします |
| 受験申込期間 | 2024年11月1日(金)~11月29日(金) | 申込期限を過ぎると受験できません。スケジュールに余裕を持ちましょう |
| 受験手数料 | 15,300円(受験願書に収入印紙を貼付) | 事前に必要な収入印紙を用意しておくとスムーズです |
| 合格発表 | 2025年3月14日(金)午後2時 | 厚生労働省のウェブサイトで受験番号と会場ごとに発表されます。 |
医師国試の出題基準は、最新の医療知識や現場の実情に合わせ、おおむね4~5年ごとに改定されます。
現在の基準(令和6年11月時点)は、令和6年版の基準が適用されており、出題内容と配点を理解しておくことで、効果的な学習戦略を立てたり試験当日のパフォーマンスを高めたりするうえで役立ちます。
国試に向けた準備を効率的かつ効果的に進めるうえで、これら情報をしっかりと把握しておきましょう。
医師国家試験は、以下の2つの分野に大きく分かれています。
医学の基盤となる基礎医学や総合的な臨床知識を問う分野。
・保健医療論: 健康保険制度、医療倫理、公衆衛生、疫学、法医学(例: 13%)
・予防と健康管理・増進: ワクチン接種、生活習慣改善(例: 17%)
・人体の正常構造と機能: 解剖学、生理学など(例: 9%)
・生殖、発生、成長、発達、加齢: 小児期から老年期まで(例: 9%)
・病因、病態生理: 病気の原因とそのメカニズム(例: 12%)
・症候: 主訴や症状の解釈(例: 12%)
・診察: 基本的な診察技術(例: 7%)
・検査: 臨床検査の基礎(例: 9%)
・治療: 薬物治療や手術療法(例: 13%)
各疾患や診療科ごとに必要な知識を問う分野。
・先天異常、周産期の異常、成長・発達の異常: 小児科や産科(例: 5%)
・精神・心身医学的疾患: 精神科の疾患や心身症(例: 5%)
・皮膚・頭頸部疾患: 皮膚科や耳鼻咽喉科(例: 11%)
・呼吸器・胸壁・縦隔疾患: 肺疾患など(例: 7%)
・心臓・脈管疾患: 循環器の疾患(例: 10%)
・消化器・腹壁・腹膜疾患: 胃腸、肝胆膵(例: 13%)
・血液・造血器疾患: 貧血、白血病など(例: 5%)
・腎・泌尿器・生殖器疾患: 腎疾患や生殖器系(例: 12%)
・神経・運動器疾患: 脳神経、整形外科的疾患(例: 9%)
・内分泌・代謝・栄養・乳腺疾患: 糖尿病、甲状腺疾患(例: 8%)
・アレルギー性疾患、膠原病、免疫病: リウマチや自己免疫疾患(例: 5%)
・感染性疾患: 細菌、ウイルス、真菌感染症(例: 8%)
・生活環境因子・職業性因子による疾患: 職業病、環境医学(例: 5%)
医師国試の問題数や配点、合格基準は以下の通りです。
| 問題区分 | 出題数 | 配点 | 合格基準 |
|---|---|---|---|
| 必修問題 | 50問 | 200点(1問4点) | 160点以上(80%以上) |
| 一般問題 | 200問 | 200点(1問1点) | 総得点基準に含まれる |
| 臨床実地問題 | 150問 | 300点(1問2点) | 総得点基準に含まれる |
| 総合計 | 400問 | 700点満点 | おおよそ400点以上(約60%) |
年度ごとの問題の難易度により、合格基準は調整される可能性があります(例えば、全体の得点率が多少上下する場合があります)。
医師国試は範囲が広いので、出題基準をもとに学習の優先順位をしっかりとつけて進めるのが大切です。配点の高い臨床実地問題においては、効率的な学習と実践力が求められ、特に禁忌肢問題は注意が必要で、解答時には慎重に判断するよう心がけましょう。最新の出題基準を踏まえ、効率的に学べるツールを選択・活用し、計画的に学習を進めるようにしましょう。
医師国家試験は、比較的高い合格率を持つ試験とされていますが、医学部入学から国試までの過程を考えると、その難易度は非常に高いものです。以下では、これまでの医師国家試験の合格率、難易度、受験者数の推移について詳しく解説します。
医師国試の合格率は、過去10年ほど安定して90%前後を維持しています。2024年の合格率は92.4%、2023年は91.6%と、近年はやや上昇傾向です。ただし90%を下回った年もあって、受験者全員が合格できる試験ではないことがわかります。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 10,500人 | 9,702人 | 92.4% |
| 2023年 | 10,300人 | 9,442人 | 91.6% |
| 2022年 | 10,100人 | 9,110人 | 90.2% |
医師国家試験の合格率の高さは、医学部での厳しい学習を乗り越えた受験者だからこそです。試験には以下の合格基準が設定されています。
繰り返しになりますが、禁忌肢問題では、医師として絶対に選んではいけない解答を誤って選ぶことがないよう、高い倫理観と慎重さが求められます。
受験者数は11年前から増加傾向にあります。2018年に1万人を超え、その後も安定的に推移しています。ただし、2021年はコロナ禍の影響で一時的に9,000人台に減少しましたが、2022年以降は再び1万人台に回復しました。
| 年度 | 受験者数 |
|---|---|
| 2022年 | 10,100人 |
| 2021年 | 9,800人 |
| 2020年 | 10,200人 |
医師国家試験を突破するためには、以下のポイントが鍵になります。
1.反復練習
必修問題や臨床実地問題でのケアレスミスを防ぐため、過去問を繰り返し解く
2.計画的な準備
広範囲にわたる試験範囲をカバーするため、優先順位をつけた学習計画が必要
3.弱点の補強
自分の苦手分野を明確にし、重点的に対策することで合格の可能性を高められる
医師国家試験は、医療の最前線に立つための第一歩。計画的に学習を進めて、確実に合格を目指しましょう。
医師国家試験に合格した後は、医師免許証の申請手続きが必要です。以下では、申請から受け取りまでの流れを詳しく説明します。
| 手続き段階 | 詳細 |
|---|---|
| 合格発表 | 厚生労働省サイトで、受験番号や試験地の結果が公開されます。 |
| 合格証書(はがき)の到着 | 合格者には厚生労働省から郵送で通知が届きます。このはがきが申請に必要です。 |
| 免許申請 | 住所地を管轄する保健所または県庁に申請書類を提出します。 |
| 医師名簿への登録 | 提出された申請書類は厚生労働省で審査され、医師名簿に登録されます(約1~2ヶ月)。 |
| 免許証の受取 | 名簿登録後、医師免許証が発行され、申請した保健所または県庁から手元に届きます(さらに1~2ヶ月)。 |
申請に必要な書類は、以下のとおりです
| 手続き段階 | 詳細 |
|---|---|
| 合格発表 | 厚生労働省サイトで、受験番号や試験地の結果が公開されます。 |
| 合格証書(はがき)の到着 | 合格者には厚生労働省から郵送で通知が届きます。このはがきが申請に必要です。 |
| 免許申請 | 住所地を管轄する保健所または県庁に申請書類を提出します。 |
| 医師名簿への登録 | 提出された申請書類は厚生労働省で審査され、医師名簿に登録されます(約1~2ヶ月)。 |
| 免許証の受取 | 名簿登録後、医師免許証が発行され、申請した保健所または県庁から手元に届きます(さらに1~2ヶ月)。 |
登録済証明書を希望する場合
1.申請先の確認
住所地を管轄する保健所や県庁が受付窓口となります。一部の保健所では受付していない場合もあるため、事前に各都道府県の公式サイトで確認してください。
2.手続き期間
免許証が手元に届くまで、申請から約2~3ヶ月かかります。登録済証明書を必要とする場合は、早めに手続きを進めましょう。
3.登録済証明書の利用
一部の職場では、免許証の到着前に登録済証明書の提出を求められることがあります。必要に応じて、保健所またはオンライン申請で取得してください。
手続きに時間がかかります。早めに準備を進めましょう。