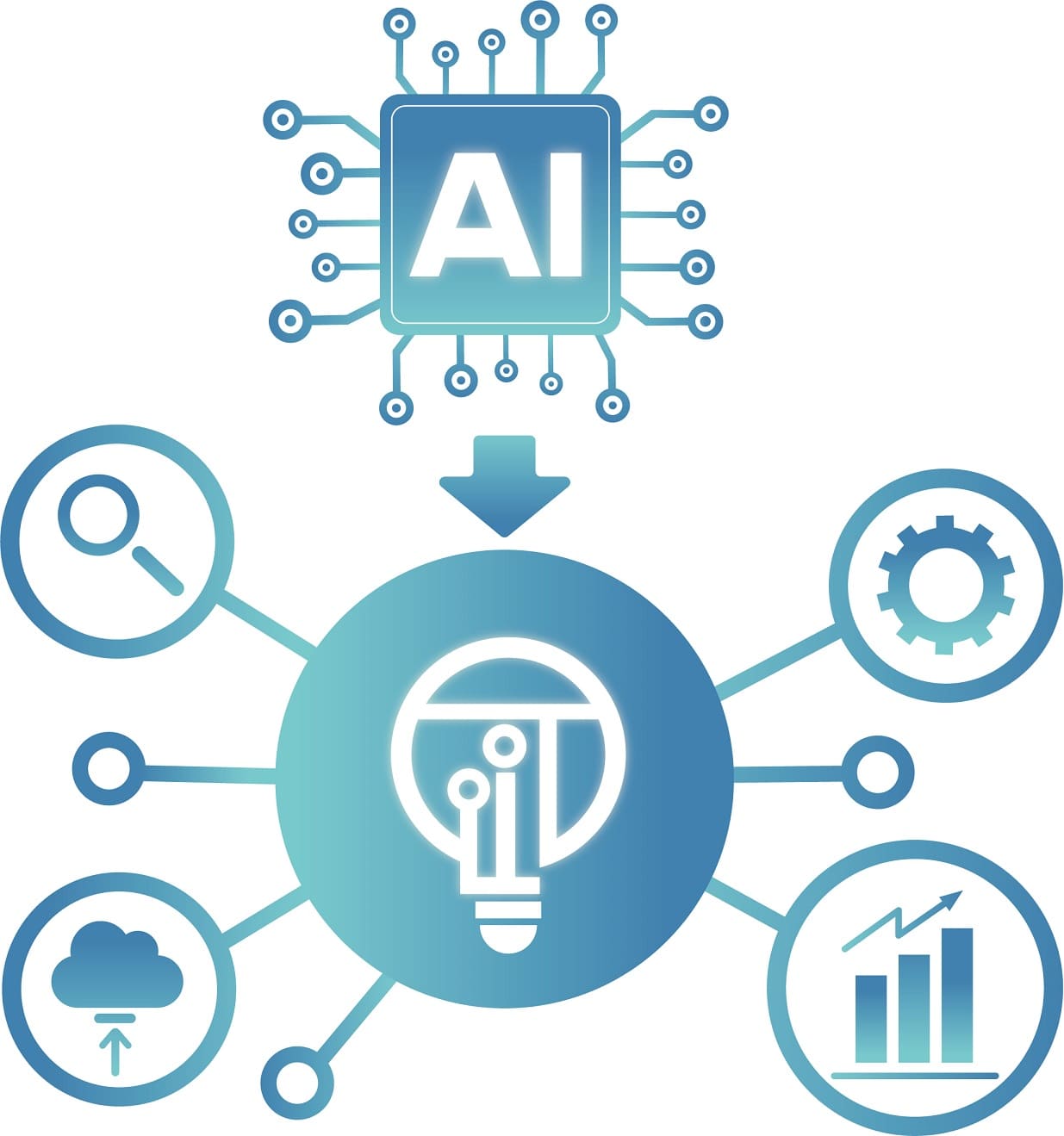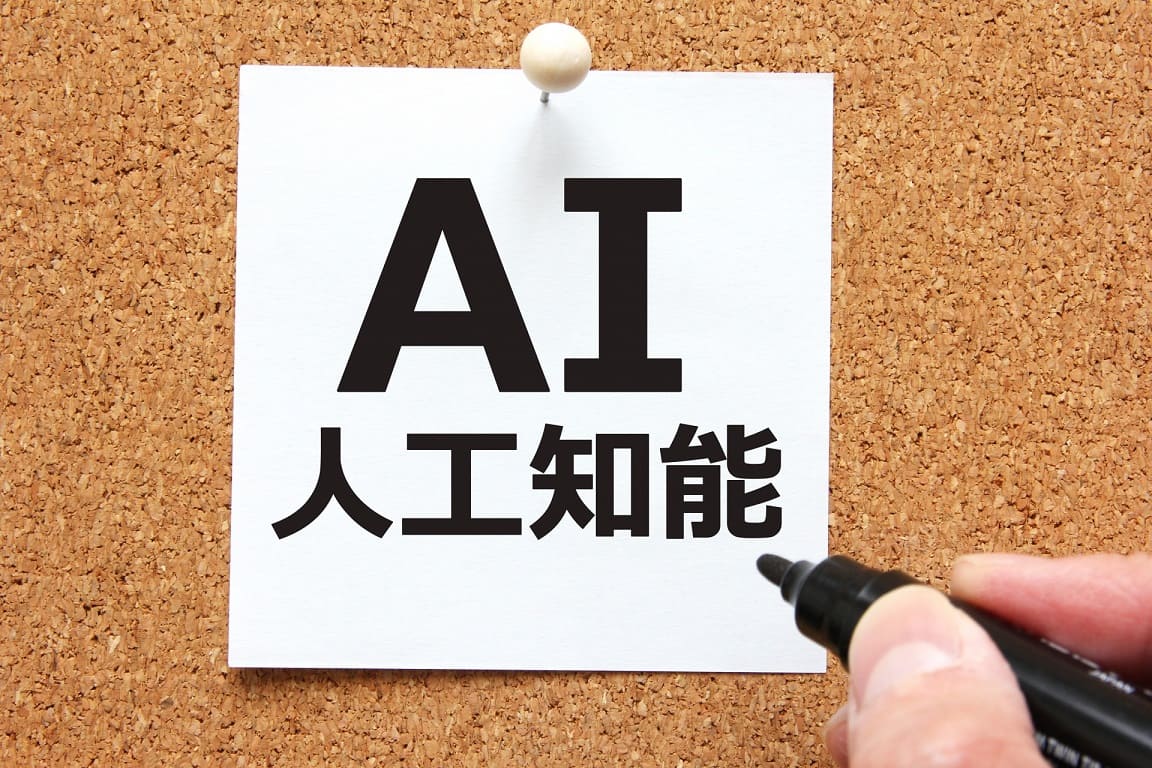
近年AIが注目され、その活用が進んでいる理由として挙げられるのは、ビックデータの活用の進化とディープラーニングの技術的進化と言われています。
ビッグデータの活用は、インターネットが普及してクラウド技術の進化によって、これまでにない大規模でデータを収集したり保存したりできるようになりました。
例えば、ソーシャルメディアが勢いよく増加し、画像やテキスト、音声などの多様な形式のビッグデータを生成しています。
AIは、こういった大量のデータから学習することで、高度な判断を下すことができるため、豊富なデータが増え続けていることが、AIの発展を後押ししています。
また、ディープラーニングの技術的な進歩も、AIの可能性を大きく広げた要素と言えます。
ディープラーニングは人間の脳の仕組みを模倣したニューラルネットワークを用いており、以前から高い潜在能力が注目されていました。
以前、計算能力の不足やアルゴリズムの未熟さなどが目立っていましたが、計算速度の向上やアルゴリズムの改良などにより、課題は次々と解決されてきています。
これら2つの進化によって、AIは複雑なタスクを高い精度でこなせるようになり、日常生活においては、自動運転車や医療診断支援、音声認識などの応用が加速しています。
今後も医療業界ではAIの活用が加速し、あらゆる分野に浸透していくことが予想されますので、医師のサポートに役立つ機能が増えていくことに注目していただきたいです。
AIもまだまだ不完全で、医師の代わりとなることは出来ませんし、正しい状況判断や直接患者に触れて感じることは、医師にしかできないことです。
MEDICALAIGOALの生成AI学習で医師としての質を高め、AIと共存してより良い医療の発展を目指していただきたいです。

近年、ChatGPTをはじめとする生成AI技術の発展により、学習方法は大きな転換期を迎えています。
従来の自らが教科書や問題集に向かっていく一方通行の学習から、AIとの対話を通じた双方向の学習へと進化しつつあります。
このテクノロジーを味方につけることで、受験勉強の効率と効果を大幅に向上させることが可能になりました。
実際にAIを使って、学習の習熟度に応じて、学習カリキュラムを受験生ごとに設計したり問題を選定することで、無理のない学習をサポートしてくれます。
また、間違えてしまった苦手な部分を、繰り返し学習することで知識の定着を推し進め、理解が進んでいる部分に関しては復習をスキップするなど、学習の効率化を図ることも可能です。
過去問から効果的な演習問題を提供するといったサービスも続々と登場し、AIはあらゆる角度から受験を支援するツールとして、今では大手の予備校や塾、そして様々なアプリやソフトに活用されています。
今後はAI機能に頼ったツールが当たり前のように教育現場へと関わっていき、個々に対してより適切な勉強法や指導を行う事に活躍してくれることでしょう。
また、AIが浸透していけば試験の内容が見直されることをも考えられます。
AIが日常にどんどん進出していけば、人にしかできない部分をどう伸ばしていくかが社会全体の課題にもなってくるはずです。
そうなってくると、ただの暗記科目ならば人でなくてAIでも事が足りてしまうため、考える力を試す問題が出てきたり、より判断が難しい問題が増えていくことも予想されます。
AIの進化は受験を大きく変える可能性を秘めているのです。
まさに今、丁度飛躍的にAIが伸びている時代です。
最新の学習機能を取り入れたMEDICALAIGOALの生成AI学習を使って、医師国家試験突破への最短の道を歩んでいきましょう。
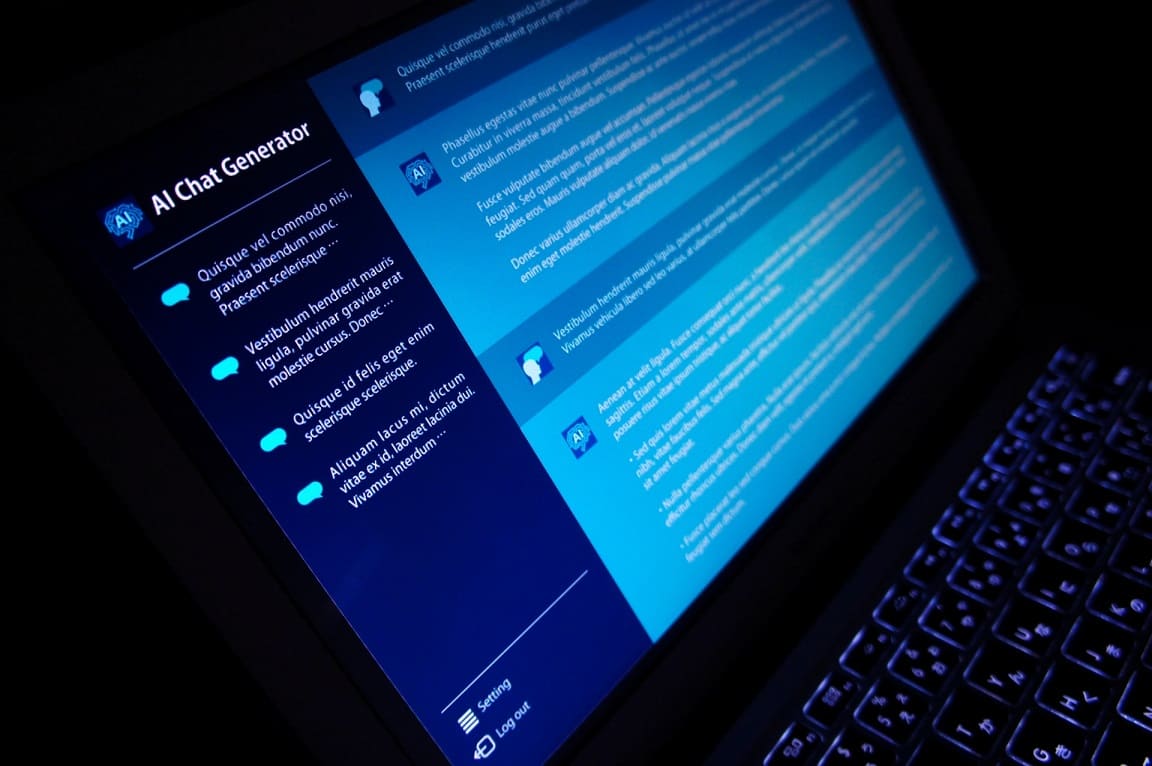
AIを使った勉強法には3つの特徴があります。
まず1つ目は、非常に多く使われているタブレット教材です。
勉強の集中力アップに最適なタブレットは、場所や時間に関係なく自分の好きなタイミングで始められるというメリットがあります。
長時間机に向かって教科書や問題集に集中することが苦手な方に、特におすすめです。
また、タブレット学習はスマートフォンやゲーム機器などと同じものを使うため、普段の息抜きの延長で、遊び感覚で勉強に取り組みやすいというメリットもありますね。
次に2つ目は、最適化された教材です。
元々勉強には「思考力・判断力・表現力」を総合的に身につけることが求められています。
医師国家試験も、この3つが必要となる問題が多々あります。
そのためには、何事もバランス良く勉強を進めていく必要がありますが、大人数で受ける講義などでは個人の理解スピードに合わせることは難しく、差が生まれてしまうことも少なくありません。
しかし、AIは個別に最適化された勉強が可能で、勉強の過程で分からない状況が起きても最適な手段で解決してくれるので、自分に寄り添った勉強法を続けることが出来るのです。
そして3つ目は、勉強の手助けです。
試験に向けて大切なことは、学習スピードを緩めないことです。
しかし、自分でも何が分からないのかが、分からなくなってしまうことはありませんか?
それを究明していくことは大切ですが、自分では中々分かり辛いという問題もあります。
そこで、AIを使えば自分がどこで躓いているのかを把握できるため、分からないことを明確にし、その克服も早めに行うことが出来ます。
今後自分が何を勉強していけば良いのかはっきり分かるため、効率的に学習スピードを上げていくことができます。
まさにMEDICALAIGOALの生成AI学習は、これらを駆使したAIの強みばかりが揃った教材と言えます。

過去問をどれだけ繰り返すかが、国家試験で点数を取れるか否かを左右します。
過去問を解いていくことで、問題の難易度や出題傾向を確認でき、そして細かいところでは問題文の文字数に慣れたり、どんな選択肢が出てくるのかを見て、ひっかけ問題等に気づくことも出来ます。
時間を測って本番さながら解くことでペース配分を掴み、2日間どのくらいの体力が必要かを実感することが出来たりもします。
過去問中心の対策によって、本番中でも見たことのある問題が多いと感じられ,落ち着いて試験に臨むことが出来たという先輩も多いようです。
これらを何度も行えば、しっかりとリハーサルが出来ているので、当日も緊張が和らいで自信を持つことが出来そうですね。
おおよそ、5年生から国家試験対策を始める方が多いのですが、この時期は解けない問題もまだまだ多い時期だとは思います。
5年が終わるまでに過去問を3~5年分を1度解いておくことや、問題集を1周しておくことをおすすめします。
たとえ解けなくても、答えを見ながら傾向を掴みつつ知識を増やしていくことが、後々勉強スピードをアップさせるのに役立ちます。
それと同時に自分の苦手分野も見えてくるので、勉強の計画を立てやすいという利点もあります。
6年生になったら、本格的な試験対策を始めます、
夏までに同じ問題集を何周も繰り返して確実に知識を定着させつつ、何年分もの過去問を再び解き、完璧に理解できるように詰めていきます。
ようやく問題が解けるようになってきたら、さらに深い勉強をするために参考書を読んだり、模試を受けて腕試しをしておくのも大切です。
そして、秋頃からはひたすら過去問を解くことを繰り返し、実際のテストでスピーディーに解く力を養っていきます。
この反復練習にMEDICALAIGOALの生成AI学習が大活躍です。
間違えた問題のみをやり直すことも可能ですし、苦手科目のみを選んで解くことも可能です。
一問一答形式で、数多くの問題を見ることが出来るので、試験当日どんな問題が出ても怖くありません。

医師国家試験に合格するために、学校の授業の予習復習や実習の準備とは別に、5年生から少しずつ対策を始める人は、1日に1~2時間程度は勉強時間をとるようです。
休日は苦手問題の克服のために、空いている時間はなるべく勉強に充てるように工夫したり、午前中は勉強時間と決めて、平日の倍ほどの時間を国家試験対策に充てると言います。
6年生になると国家試験までの間に卒業試験等もあるため、その期間の勉強時間は1日12時間以上、もしくは起きている間、最低限の身支度の時間以外は全て勉強に費やすという方も少なくありません。
また、人に❝教える・説明する❞という勉強法も自分の知識の定着に良い効果があります、
自分が説明できないということは完全に理解できていないという認識も出来るため、学校にいる間に積極的に友人等と問題を出し合って勉強するという方法もあるようです。
仲間意識を持って頑張ることで、モチベーション維持にも繋がります。
卒業試験の勉強は国家試験対策にも繋がっているため、実際には国家試験のための勉強とも言えますね。
そして、6年生は学校の試験や授業以外でも、国家試験のために休日どちらか1日はずっと勉強、もう片方の休日はアルバイトやリフレッシュ時間との両立で5時間程度、平日でも最低3~4時間は確実にとるようにしているという方が多いようす。
特に国家試験の直前期は演習量で決まると言われ、追い込みで最低でも1日12時間以上、年が明けてからは、1日18時間ペースで勉強したという、詰め込み型の方もいらっしゃるようです。
追い込み期は、1日にやらなければならない分量が膨大になり、18時間勉強でも足らず、1分でも惜しかったので大学の卒業式を欠席する方もいるほどだそうです。
大学受験以上の勉強時間が必要ともなれば、使用する教材次第で時短や効率化を図ることは絶対やって損はないはずです。
MEDICALAIGOALの生成AI学習は、勉強の進捗状況を示し、合格までの道筋を照らしてくれますので、勉強に追われている期間に手が回らない自分の現状把握を担ってくれます。

試験日までを逆算して年間の勉強スケジュールを立てることは、試験突破のカギと言えます。
特に苦手分野がはっきりしている場合、その部分を重点的に取り組むことが効果的です。
例えば範囲を狭めて考えてみると、月間計画では自己の苦手意識のある単元を明確にし、それらに焦点を当てることが必要です。
大雑把にでも苦手科目を挙げておくことが有効です。
もっと短い週間計画では、月間計画で設定した大雑把な目標を具体的な課題に分解します。
演習を通じて自身の課題を明確化し、それに対応する形で計画を細分化することがポイントです。
さらに短く日々の計画では、制限時間を意識して、目標とする勉強量を決めることが重要です。
例えば、1日50問解く、この科目の問題集を10ページ解く・・・など、日課を設定しましょう。
また、計画はその時に応じて柔軟に修正することも大切です。
計画が狂った時には、なぜそうなった原因を分析し、次の計画に活かすことも大切です。
MEDICALAIGOALの生成AI学習は、AIが進捗状況や今どのくらい問題を解いたのか等を集計してくれるので、とても分かりやすいです。
科目ごと正答率を割り出してくれるので、自分がどのくらい勉強が足りていないかも目に見えてわかります。
客観的に自分を見ることが出来るため、無駄のないスケジュール作りに力を貸してくれますよ。
医師国家試験合格にはたくさんの演習量が必要ですので、スケジュールを立てる上で重要なのは、❝理解できるまで繰り返して反復演習を行えるようにする❞ことです。

医師国家試験のために長期間集中して勉強するためには、勉強しやすい環境を整えることも大切です。
まず1つ目として、規則正しい日々を過ごすことが重要です。
規則正しい毎日を送ることは、メンタルと体調の維持に大きく貢献します。
体調が良い状態ならば脳内もスッキリしていますので、自然と集中力が湧いてきます。
この規則正しさには、勉強の時間もなるべく日課となるように決まった時間、決まった量をこなすというのも含まれています。
朝起きて家を出る前の10分や電車に乗っている間の30分、帰宅して寝る前の1時間・・・など、どの時間を勉強に充てるのか決め、それがルーティンのように当たり前にこなせるようになれば、ストレスも軽減されます。
このルーティンを作るのに、MEDICALAIGOALの生成AI学習はサクっと短時間に集中して勉強するのに便利なルールですので、取り入れやすいでしょう。
また2つ目はルーティンと併せてスケジュールを立てて勉強に取り組むというのも、日々の目標が設定されるのでやる気がアップしやすいです。
行き当たりばったりで勉強を進めていては、どんなに優れた環境に身を置いていたとしても、学習の進捗に悪影響が出てしまうでしょう。
AIは自分の勉強量や進捗状況を管理しているので、スケジュールを立てるのにとても便利です。
最後の3つ目は時々勉強場所を変更してみることです。
毎日自宅学習している場合は、たまには図書館へ行ってみたり、近くのカフェや喫茶店へ行ってみるのも良いでしょう。
意外とシーンとした静かな場所よりも、カフェなどで雑音が入る方が集中しやすい方もいらっしゃるようです。
お気に入りの場所が見つかれば勉強も楽しくなりますし、移動することで下半身の運動が伴うので、血行が良くなり脳内の疲労のリセットも狙えます。
WEBブラウザで行う学習は、どんな場所でも周りに気を遣うことなく出来るという利点があります。
その時の状況に対応できる分、勉強を始めるまでのハードルも下がりますね。

医師国家試験の問題形式は問題の内容や構造、正答肢数など色々な分け方があります。
大きく分けて3つ、研修医になるための最低限の知識を問う「必修」、疾患ごとの知識を問う「各論」、疾患を跨いで横断的に問う「総論」です。
1日に各論・必修・総論の試験が1コマずつ実施され、どの分類の問題もその構造によって特定のテーマを明示され、「〇〇制度について正しいのはどれか」や「〇〇症状に関して誤っている選択肢はどれか」など、知識が問われる一般問題と、例えば「○歳の○性が○○の症状を・・・」などの症例提示で始まる臨床問題の2つに分けられます。
一般問題と臨床問題があり、各50問ずつ合計100問出題され、試験は全てマークシート方式で、ほとんどが5肢1択形式です。
必修は基礎医学、臨床医学、社会医学など、大学生活の6年間で学んだすべての医学関連科目が出題範囲として設定されているため、幅広い知識が問われます。
患者と会話して診療に必要な話を聞き出す「医療面接」や診療を行うための「医学英語」といった、受験生にとってあまりなじみのないテーマからの出題もあるので要注意です。
試験は2日間にわたって行われ、朝から晩まで目一杯詰まっています。
試験開始は9時30分から、そして試験終了は18時30分ですので、長時間試験に集中するための体力も必要です。
集中力に自信がない方は、この時間ずっと緊張感を保って問題を解くという状況に慣れるため、同じ時間割で勉強する機会を多く持つようにしてみてください。
本番さながらリハーサルを重ねておくと良いでしょう。
試験の時間割のように、時間を区切って科目を変えながらひたすら問題を解いていく作業は、MEDICALAIGOALの生成AI学習がピッタリです。
過去問をもとに問題を作っているので、問題形式にも慣れることできますので、解くスピードもアップしていくことが実感でき、本番でも時間配分に焦らず解けるようになるでしょう。
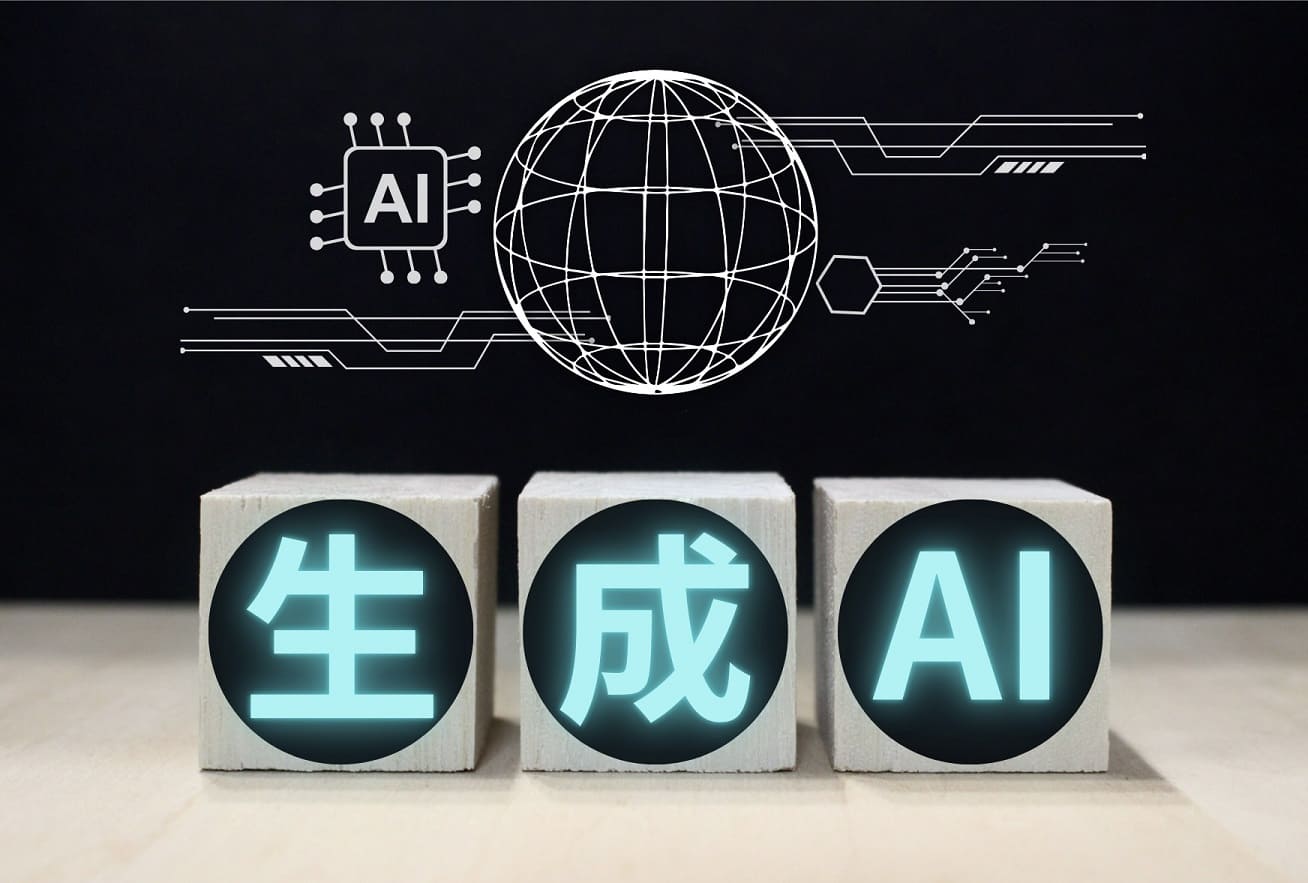
国家試験では、「基礎医学・臨床医学・社会医学」など、医学関連科目の全てが出題範囲となります。
しかし、全ての分野から均等に出題されるわけではなく、近年の国家試験で特に出題割合が高かったのは、「消化器・循環器・内分泌代謝・呼吸器・神経・小児科・産科・公衆衛生・救急・感染症・精神科・医学総論」の12科目です。
このうちメジャー科目と呼ばれるのは最初の1~7個目までの科目で、これらについては毎年出題率が高いので、早めに対策するのがおすすめです。
また、他の受験生もメジャー科目については必ず勉強して挑んでくるので、正答率も高く、ここで落としてしまうとかなり勿体ないです。
また、国家試験には「出題基準」というものがあり、厚生労働省が概ね4年ごとに、医師国家試験に出題する範囲と疾患をリスト化して公表していますので、一度目を通しておいてください。
前年と比較して変更されている多く、直近で見てみますと、産科で「可逆性後頭葉白質脳症〈PRES〉」、「周産期心筋症」などが新たに明記されたり、眼科で目の先天異常に関する項目が項目ごと削除されたりしています。
医療業界は日々新しいことが発見されたり、情報が古くなっていったりします。
アップデートを忘れずに、出題基準や頻出問題を分析し、しっかりと対策していきましょう。
その分析はMEDICALAIGOALの生成AI学習が得意です。
自ら手間をかけなくとも、現役医師が監修して本当に出る問題を集め、過去問の分析から予測した問題によって、合格率をアップしてくれます。
さすがはAI、得意の分析で医師国家試験を前面サポートしてくれますよ。

必修問題のうち、一般問題50問、臨床実施問題50問、点数配分は一般問題1問1点で臨床問題は1問3点であり、必修の合格基準はその年の難易度に関わらず80%(160点以上)です。
それを下回ると他が満点でも必ず不合格になってしまいますので、合格ボーダーの8割を意識しながら勉強していきましょう。
また、必修以外の一般問題と臨床実施問題は300問出題され、1問1点で230点以上取る必要があります。
これらを合計すると、全400問の500点満点で、合格には390点以上が必要となります。
ちなみに、必修問題を除いた一般問題および臨床実地問題の合格基準は例年変動し、約70〜77%で推移しています。
そして1番の要注意事項として、医師国家試験には「禁忌肢」というもう1つの絶対基準が設けられているのをご存じでしょうか?
禁忌肢は医師としての適性に欠ける者をはじくために作られたもので、例えば患者を死なせてしまったり、臓器の機能が二度と戻らない状態につながったりという、医師として倫理的に許されない事項を含む選択肢のことです。
禁忌肢の数は年によって違いますが、禁忌肢を4つ選んだ時点で、他でどれだけ点数が取れていても、たとえ
他が満点であったとしても不合格となってしまうため、禁忌肢対策も必要です。
これらを知ったうえで勉強しなければ試験対策にはなりません。
独自で進めるよりも、MEDICALAIGOALの生成AI学習のように、本当に試験対策となる過去問や予測問題が詰まった教材に触れ、解き慣れておくことが重要です。

MEDICALAIGOALの生成AI学習では、2024年現在、以下の27種類のカテゴリを取り揃えています。
「ランダム・消化官・肝胆膵・循環器・代謝内分泌・腎・アレ膠・血液・感染症・呼吸器・神経・中毒・救急・麻酔・医学総論・小児科・産科・婦人科・乳腺外科・眼科・耳鼻咽喉科・整形外科・精神科・皮膚科・泌尿器科・放射線科・老年医学」
細かく科目を絞って勉強出来ることで苦手対策しやすい内容となっており、そして各科目で出題されやすい問題をまとめているので、使用回数を重ねるごとに確実に得点へと繋げていくことが出来ます。
例年出題数の多い「循環器・呼吸器・小児科」や「産科・婦人科」をメインに解いてみたり、内科で絞って「消化管・循環器・呼吸器・精神科」等で絞ってみたり・・・
学習スケジュールに合わせて、一定期間で科目をいくつか絞って克服していくのにも、とても使いやすいのです。
慣れてきたらランダムのカテゴリを選んでバランスよくあらゆる分野からの問題を解くことで、判断力やバラバラの分野への思考の切り替え等を鍛えることが出来るようになります。
定期的にどれだけどの分野の正答率が上がっているのか等を確認しながら、本番に向けてリハーサルしていきましょう。
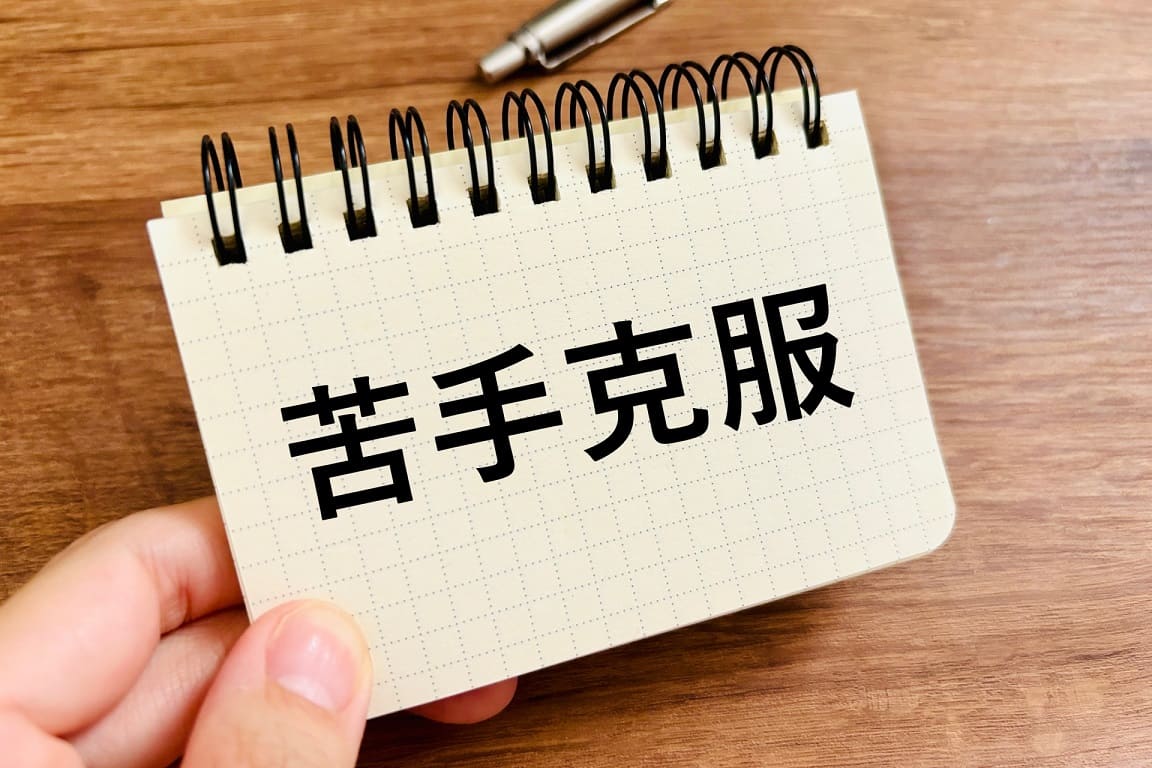
医師国家試験が直前に迫ってくると、どれだけ勉強していても気持ちが落ち着かないという状況に陥る方も少なくありません。
焦って手あたり次第目の前にある参考書を開いてしまったり、何度も解いて正解している問題を眺めていたらあっという間に時間が経ってしまって、有意義な時間を過ごせなかったという失敗談もあります。
ですので、直線期には何をすべきか自分の中で決めておくことも大切です。
まずは何より、体調管理をしておきましょう。
どれだけ勉強しても、本番当日体調が悪ければ試験に失敗してしまうかもしれません。
当日は体力勝負でもありますから、事前に当日の朝昼に食べるもの決めておいたり、どうしたら自分の集中を保てるのか、ルーティンを決めておくのも精神が安定しやすいと言われています。
そのためにも、直前で短期集中型の無茶な勉強をするよりも、普段から計画的に勉強しておくことも大切なのです。
確認作業は、出題されやすい問題や自分の苦手な科目、そして過去に間違えてしまった問題を中心に行っていきましょう。
覚えるのが苦手な科目や、これまで間違えたところをピックアップしておくことが必要ですが、MEDICALAIGOALのAIがそれを代わりにやってくれるので、とても手間が省けます。
試験前日に確認したいものも、ソフトを使って決めておくと短時間で集中的に最終確認が出来ますね。
MEDICALAIGOALの生成AI学習は過去問から問題を予測し、試験内容に合わせたものを出してくれるので、これで勉強するのが1番本番で力を発揮できるはずです。
直前期の見直しはもちろんのこと、日課の勉強ツールとして使いたい方にもおすすめです。
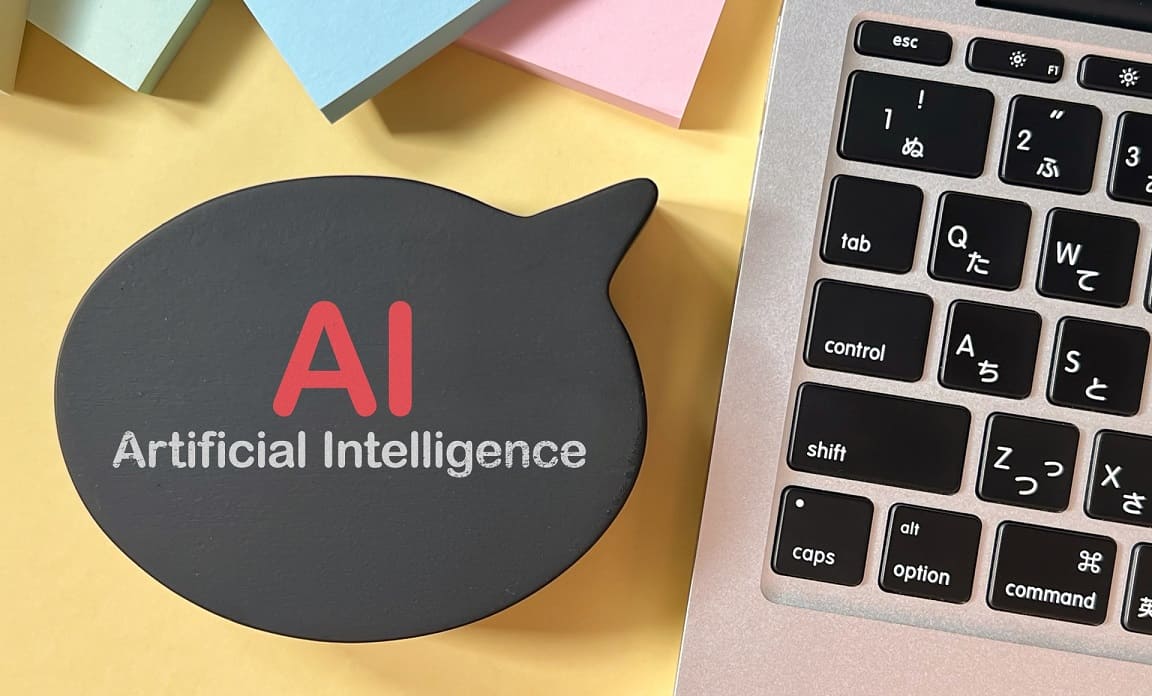
浪人生は外部との関わりが薄くなりがちで、現役生と比べて最新の医学に関する知識や、国家試験に関する情報等が手に入りにくくなるという弱点があります。
国家試験は情報戦でもあり、実際に都市部で医学部の集中している地域は合格率が高いという結果もあります。
その為、いかに合格のための情報を手に入れるかが重要となってきます。
国試浪人となった場合、浪人仲間や現役生の仲間を見つけて情報交換をしたり、予備校などに通って最新情報を手に入れられる環境に身を置くことが望ましいです。
しかし、中には仕事をしながら勉強しなくてはいけない方もいらっしゃいますし、自宅で勉強を続ける方が性に合っているという方もいらっしゃるでしょう。
そういった場合には、国家試験の最新情報を反映したMEDICALAIGOALの生成AI学習がおすすめです。
これならば、自宅で勉強しながらも、情報がどんどん入ってきますね。
実は、本来ならば過去問に重点置いて分析と傾向を掴んで勉強するのが正しい勉強法ですが、浪人生は時間的余裕から細かい知識を詰め込もうとする傾向があり、王道の勉強方法から外れてしまい、またもや合格率を下げてしまう危険性があるとも言われています。
そうならない為にも、AIはとても役立ちます。
本当に必要な勉強が出来るように、過去問から割り出した頻出問題を中心に出題し、また苦手科目などの弱点を集中的に克服するよう、アシストしてくれます。
予備校では全て賄ってもらえますが、独自では難しいとされる進捗状況やスケジュール管理もしてもらえるので、客観的に自分を見つめ直すこともでき、誤った対策をしないよう軌道修正してくれるのです。
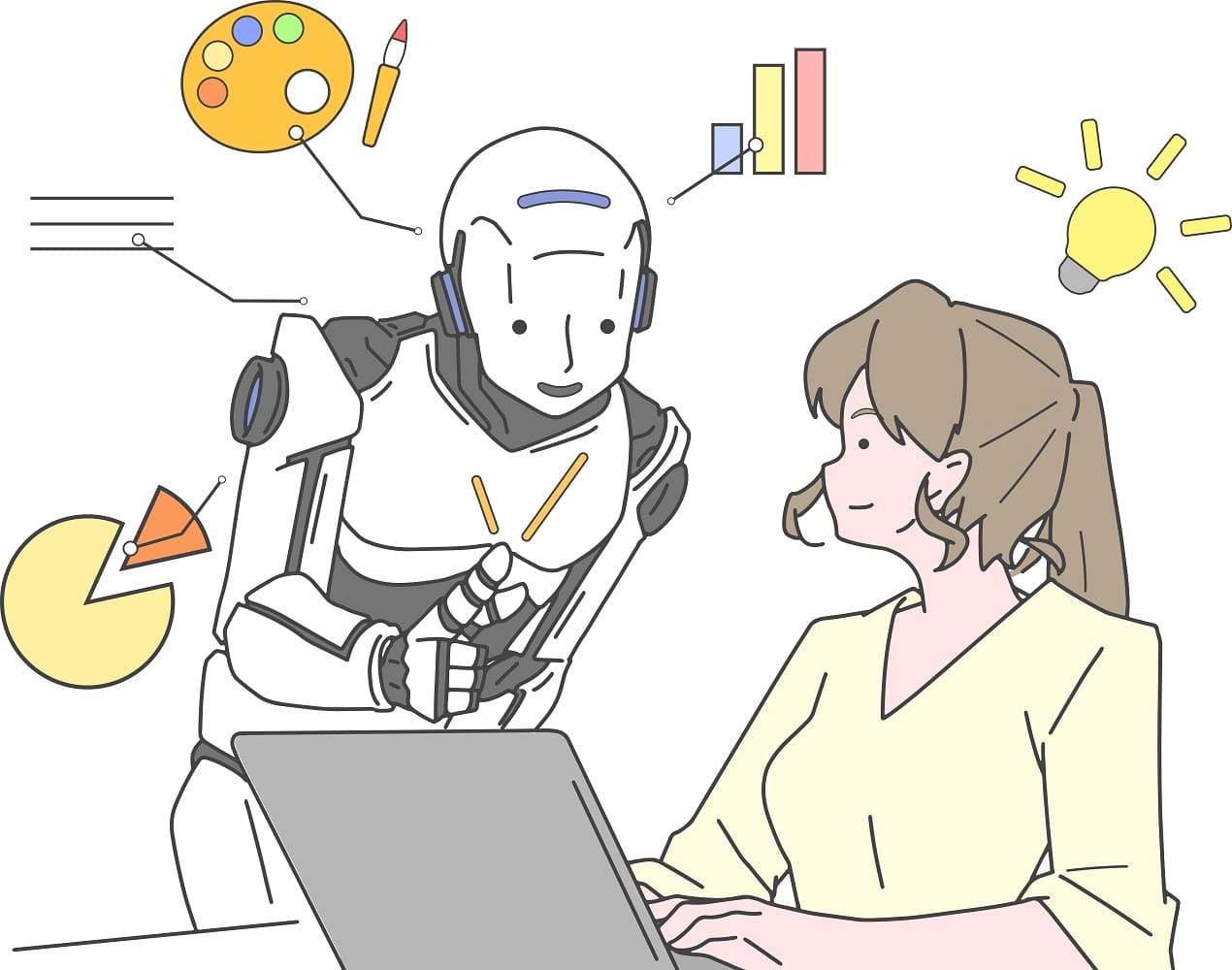
弱点克服は、分かりやすい解説と試験を熟知した効果的な教材を使わなければ、得点へと結びつきません。
そこで有力候補なのがMEDICALAIGOALの生成AI学習です。
優秀な分析力を持ちあわせた効果的な学習ツールだということが、ご理解いただけたかと思います。
予備校やオンライン授業以外にも、今では選択肢がたくさんあることを覚えておいてください。